◇映画「グスコーブドリの伝記」を観る(ネタバレ注意) ― 2012年07月16日 14時49分36秒
映画『グスコーブドリの伝記』予告編【HD】 2012年7月7日公開
昨年の東北地方の震災と、それに伴う原子力発電所の事故などから、私はずっと「グスコーブドリの伝記」に出てくるような研究者が日本を救ってくれないだろうかと、ちょっと本気で思っていた。
現実は、自身の企業生命を維持するために消費者を省みない電力会社と役立たずの政府だけがクローズアップし、原子力発電所の事故を解消・解明するために投入された技術はほとんどが役立にたたないというニュースばかりで、ブドリやペンネン所長、クーボー博士のような人が表に出てくることは今のところ聞こえてはこない。
つくば時代に国の研究所で働いていて、多くの研究者がどのような人たちで、それを管轄するお役所がどのようにふだん仕事をしているのかは、いやというほど見てきたのだから、こんな甘い幻想をするほうがどうかしていたのだと思ったりもするのだが。
それでも、今この時期に「宮沢賢治のグスコーブドリの伝記」を映画化することには、ものすごく大きな意味があるように思っていた。
キャラクターデザインが、ますむら・ひろしのものであることも、楽しみの一つでもあった。彼は宮沢賢治に感銘を受け、自身の猫のキャラクターで、ずっと宮沢賢治の物語を漫画化してきたからだ。
しかし、映画を観た感想として、宮沢賢治の原作を読み、ますむら・ひろしの漫画に非常に感銘を受けた私にとっては、この映画は非常に残念でならない。がっかりしたを通り越して、宮沢賢治の名前を語った違う宗教に勧誘されたくらいの違和感を覚えた。
ネタバレも含む内容かもしれないので、これから読む人で楽しみにしている人は、この先は読まないでほしいと思う。
というか、これから観るのを楽しみにしている人は、こんな一般人のレビューなど検索して読んではいけない。せめて公式ホームページであらすじと出演キャラのチェックをする程度にしておいたほうが無難だ。
この文章は、映画を観てがっかりしたという人にだけ読んでほしい。
この文章を読んで、「先入観植え付けられた」とか後で文句を言われても、私は一切責任をとらないので、ご了承のほどを。
グスコーブドリの伝記公式ホームページ
http://wwws.warnerbros.co.jp/budori/
※澤 穂希は、オリンピック前にこんなところで余計な仕事してんじゃねーよ、とアクセスしたときに思ってしまった(^^;)。
映画の世界観は、これだけとってみればまあ素晴らしいものだろうとも思うし、映像も違和感を感じる部分はあっても、美しいと思えるものであった。
ブドリの顔がこれほどまでに、声を担当した小栗旬に似ているように感じたのも面白かった。彼の演技やバラエティなどで見るキャラクター性などは好きではないが、この声の淡々とした演技ははまっていたようにも思える。
実際、同じ映画館で見た家族連れの子供は、映画が始まるまではポップコーンの箱をがさがさとしてうるさくしていたのが、映画が進むにつれて静かになり、帰るときには両親にブドリの無事を質問するまでになっていた。
原作を知らない様子の両親は、ブドリが実際どうなったのかを説明できる状況にはなく、笑ってごまかすばかりだったのも印象的ではあったのだが。
大人の中には泣いている人もいた。
テーマとしては感動的だし、現代社会を啓蒙した内容であっただろうとも思う。
しかし、私はその中で一人怒り狂っていた。
この物語を宮沢賢治のお話としてとらえるならば、これは宮沢賢治の物語ではないだろう。
彼が物語の中で語っていた重要性の方向がまったく違うところに存在するし、メッセージも違うものに置き換えられている。
宮沢賢治の時代と違うからとかそういうものではなく、今この時だからこそ「グスコーブドリの伝記」が必要であるということが、まるっきり無視された内容になっているのだ。
ますむら・ひろしの「グスコーブドリの伝記」は、できるだけ宮沢賢治のメッセージを壊さないように細心の注意を払われて作成されているのが、読むと手に取るように解る。それなのに、この映画にはその繊細ささえもぶち壊しているようにしか感じられなかった。
この映画で、ますむら・ひろしのキャラクターを使用する必然がどこにあるのか。
「銀河鉄道の夜」のときと同様に、ますむら・ひろしが今回の映画でも、キャラクターデザインとして採用されている。彼のキャラクターは印象的だし、その特異性から絶対に他の人のキャラと間違えたりすることはない。
すでに公開から20年近い年月が経っている、「銀河鉄道の夜」のイメージを壊さないようにするためなのか。
それとも、「銀河鉄道の夜」にもつなげ、宮沢賢治の世界を広げようと言い戦略か。
その両方なのか。
監督が同じ杉井ギザブローであることや、「グスコーブドリの伝記」の中にも「銀河鉄道の夜」つながるモチーフがちりばめられていることを考えると好意的に受け取りたいが、何か商業的な戦略が見え隠れする。
映画の世界観としては、宮沢賢治やますむら・ひろしの描いた田舎の風景と田舎の地方都市イーハトーブとは異なる。これは映像的にもう少し具体的な世界観を描く必要があるせいもあるから、物語や漫画と違っていても仕方がない部分はあると思う。
だが、どこかレトロ感漂う近未来的世界は、なんだか宮崎駿を意識させ、ブドリの見る夢の世界は「千と千尋の神隠し」みたいだった。
アニメーションは手塚プロが手がけている。
監督 杉井ギサブローが手塚プロを使って宮崎駿の世界をますむら・ひろしのキャラクターで表現したのがこの映画だが、それくらい統一感のない違和感の残る映画だった。
(この夢の世界の監修として、旧友の名前をエンドロールで見つけてびっくりしたが。彼はこのような世界観に使用されることを知っていたのだろうか。映像的にはうまくできていたが。)
原作には映画ではカットされてしまった重要なシーンがいくつもある。
ネリがさらわれた後、家をテグス工場にのっとられたところや、その後のこと。
赤ひげが山師ばった農業を行なった時間感覚。
クーボー博士の講義に出たときに質問された、煙突から出る煙の特徴を語るシーン。
火山局の研究員として活躍するブドリの元に、離れ離れになっていたネリが訪ねていくシーン。
森に行ってしまった両親のその後の情報。などなどなど・・・・
最後の火山のエピソードにしても、ブドリは研究者として非常に勇敢な行動をとるし、ペンネン所長もクーボー博士も決してブドリの考えに耳を傾けなかったわけではない。
原作のラストは、あくまで火山局の職員として、ブドリは行動するのだ。
あれは火山局がイーハトーブの住民のために、総力を決して行動する結果のことであり、火山局がいかに人々の暮らしに密着した存在であるのか。そこで働くブドリが、どれだけ人々のことを考えて日々研究に従事しているのかが表現されているはずなのだ。
名もない研究員が、人々の暮らしを守るために自らの命を呈して、自分の職務を遂行した。それこそが名もない人の伝記としての役割であり、ブドリの救いでもあると思う。
それなのに、この映画のラストだと、ブドリはまるでネリがさらわれてから、ずっと夢の中にいたのではないかと誤解されても仕方がないようにさえ思う。
ブドリの行動が夢ではなかったのだとしたら、ブドリは火山局の職員として上司の意思を無視した行動をとるという、一番やってはならないことをしてしまっているようにも見える。
これでは、ブドリはお世話になったペンネン所長やクーボー博士、火山局のスタッフの人に対して、自らの信念を貫くがために音を仇で返してしまったようにも受け取れる。
ブドリの意思と勇気と、研究者としての決断力が、この映画にはまるで表現されていない。
ネリの無事も確認できず、両親がその後どうなったのかも知らず、ただただ自分の諦念のために、実際に死んだのか生きているのか、夢なのか現実なのかも解らずに最後を迎えるブドリが、これではあまりにもかわいそうだ。
まして、ところどころに宮沢賢治の「雨ニモマケズ」がモチーフとして語られているのだが、その言葉のひとつひとつにとらわれすぎ(例えば「デクノボーと呼ばれ」のところとか)、その詩全体の意味さえもゆがめられてしまっているようにさえ感じる。
これではすっかりブドリはただの「デクノボー」でしかないようにも感じる。
確かに自然環境における人間の無力さなども、この物語のテーマではあると思うが、原作が言いたかったことはそこだろうか。
農業を愛し、自然を愛し、火山を愛し研究してきた宮沢賢治の言いたかったことが、ますむら・ひろしが猫にのせて語りたかったことが、この映画では何も語られない。
百歩ゆずって宮沢賢治の物語を独自の視点でアニメ化したとしたのなら、この物語にますむら・ひろしのキャラクターを使用する必然性は皆無ではないのか?
ますむら・ひろしの世界観をとても好きなものとしては、彼の世界観をこんな形にされて、こんな残念なことはない。
この映画が持つテーマが悪いわけではない。ただ、宮沢賢治が物語を通して言いたかったことが何も伝わらないのなら、せめてこの映画を見た人が宮沢賢治の「グスコーブドリの伝記」を読むきっかけにしてもらえたらいいのにと、切に願うばかりである。
映画を観る前にこの文章を読んでしまった気の毒な人は、せめて宮沢賢治の原作か、ますむら・ひろしの漫画を映画の後でも先でも構わないので、合わせて読んでほしい。
この映画で言っていることだけが、この物語で残すべきことではないことが理解できると思う。

宮沢賢治全集〈8〉注文の多い料理店・オツベルと象・グスコーブドリの伝記ほか (ちくま文庫) [文庫]
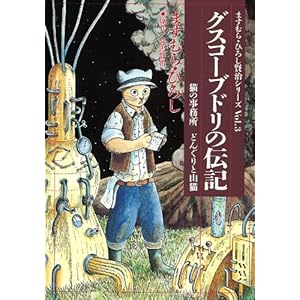
グスコーブドリの伝記―猫の事務所・どんぐりと山猫 (ますむら・ひろし賢治シリーズ)/ますむら・ひろし(amazon)
最後にひとつ思ったこと。
グリム童話の「ヘンゼルとグレーテル」は、飢饉のときに親に森に捨てられる。
グスコーブドリとグスコーネリは、飢饉のときに親が森へ行ってしまう。
このような状況下において、子供にとって、親にとって、どちらが辛い判断だろうか。
やっていることは同じなのだが、今の時代の立ち位置から見たならば、ブドリの両親の方が愛情があるように感じられるのだろうなと、なんとなく思った。
コメント
_ ルッコラ ― 2013年08月10日 22時18分42秒
私も同感。
_ makura ― 2013年08月19日 00時04分08秒
ルッコラさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
そして、同感の意思をお伝えくださり、ありがとうございます。
コメントありがとうございます。
そして、同感の意思をお伝えくださり、ありがとうございます。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。
