◇計画停電二十一日目。被災の感覚と距離、暗さに慣れる必要性。 ― 2011年04月05日 01時52分23秒
2011年4月4日月曜日 計画停電二十一日目。
3月24日の停電以降、ずっと計画停電は実施されず。
暖房需要が減ったことと、火力発電所が動き始めたからとの理由だった。
停電がしばらくなくなったことで、停電が自分の気持ちにかなりの負担になっていたことを知る。
停電になれば、お店も美容院も病院も営業しない。その時間だけというところもあるし、停電が日中に行われる日は営業そのものがなくなるところもある。
停電も朝方や昼ならいいのだが、旦那の帰宅時間に停電時間が重なると、帰路の半分くらいは信号がストップしているので、事故が心配で落ち着いていられない。
一人、真っ暗な中で心配しながら帰りを待つのは、精神的にも良くない。
そういう夜から開放されるということだけでも、計画停電がない期間が続くのは嬉しい。
先週に、自分の状態があまりにも不安定なので、パソコンをつけるのを辞めた。情報が多すぎて、自分で処理しきれなくなったからだ。
友達から携帯に心配のメールをいただいたりもしたが、その返事を入力するのに数時間かかる。状況を伝えようとするとものすごい長文になり、かといって「大丈夫、心配しないで」と配慮できる状態でもなかったらしい。
後で自分の返信を見て、あまりのひどさにさらに落ち込んだりもした。
一週間近くパソコンをつけなかったことで不便も感じたが、特に支障はなかった。地震以来仕事は入れていないし、パソコンをつける必要性もない。
停電もなかったし、必要な情報も必要でない情報も入らないことは、不安よりも開放感の方が大きかったかもしれない。
それでも、テレビのニュースは見ていたので、情報を完全に遮断していたわけではない。
どんどんと露呈される東電の事故対応の鈍さと、日本には本当の意味で原子力設備の専門家などいないのだろうか、という気持ちがいつもテレビの前にあった。
毎日テレビに出てくる原子力の専門家や、私たちがつくばで出会った原子力関連の研究者など、こんなときに何故知恵を出すような動きがないのかが不思議だ。
水を止めるのに、吸水性ポリマーと一緒におがくずと新聞紙というお粗末な顛末を見て、「順番が違うだろう」と家の中で怒号が響く毎日だ。
しかし、避難所の様子や被災者のドキュメントなどは、平静に見ていることができない。旦那も「最近、ああいうのを見ると涙が出てくる」という。
自分は被災していないつもりでも、実際に地震のゆれを感じ、地震の影響を生活に受けている私たちの気持ちは、阪神淡路や中越、奥尻島の地震のときとは明らかに違う。
被災の現実感と中途半端な距離が、心のバランスにつながっているような感覚。
こういう気持ちでいるのは、私たちだけではないような気がする。
阪神淡路のとき、私はパソコン通信(インターネットの前身のネット環境)のチャットをよく利用していて、そこでよく会う人の中には関西の人も多かった。
当時、関西の人たちは関東で地震などがあると、口をそろえて「関西は地震が少ないから、よくわからない」と言い、中には顰蹙を買う人もいた。
しかし、阪神淡路大震災の起きた後、当然のことながら状況は一変した。
つい先日まで「地震の怖さをわからない」と言っていた人も、地震がいかに怖いか、あんな大きな地震は体験してみないとわからない、というようなことを言ったりしていた。
中には、地震のオーソリティみたいになっている人もいて、関東の地震の多い地域の人から失笑を買ったりもしていた。
それでも、どうしても、あの恐怖を伝えないではいられない、という感じだった。
時間が経って、被害の大きかった地域の人がネットに戻ってきたとき、地震のことを聞いても「大変だった」「怖かった」とは言うが、あまり多くを語ろうとする人は少なく、被害の大きかった地域の人たちよりも、その周辺の人たちの方が地震の恐怖について語ることが多かった。
こういうのは、被災が大きかった人は、語る言葉をなくしてしまい、その周辺で現状をある意味客観的に肌で感じた人は、語らずにはいられないのかもしれない。
あの時はそのギャップに驚いたりもしたが、自分もその渦中にいて「あれはこういうことだったのかもしれない」と思ったりする。
この日曜日は、一週間ぶりに買い物に行った。
妹が先々週に野菜を送ってくれたので、買い物に行く必要がなかったからだ。
久しぶりに買い物に行っても、暗い店内を見回して必要なものを購入するが、なんとなく買い物をしたい気分になれない。
店内が暗いと、人が多くても活気が感じられないのだ。
ふだん家にいても、使わない部屋や廊下の電気を切ったり、居間の電灯を半分にしたりして、ふだんよりも暗い場所で生活している。
それでも、スーパーマーケットに行くと、いかに自分がそれまで明るい場所に慣れ切っていたのかが、身にしみて自覚させられてしまう。
節電自体は良いことだと思うので、停電があってもなくてもこれくらいの明るさでいいと思う反面、心のどこかで暗い気持ちになってしまう。
自分自身、早くこの暗さになれたいと思う。
ふだんは買い物しない百貨店の食品売り場で、茨城県産のロメインレタスとリーフレタスが、2把で100円で売られていた。
地震前、ロメインレタスなどはそこの売り場で、1把で300円近い値段で売られていた。
風評被害のために仕入れ値自体が安くなっているのだと思うが、この値段には素直に喜べなかった。
この値段では、たぶん農家にはいくらも収入にはならないだろうからだ。
それでも、茨城県産の野菜が百貨店で取り扱いがあるということは、とてもうれしかった。
売り場の一番目立つ場所に山積みされていたが、半分ほどなくなっていて、購入する人もいることが実証されていた。
この状態であれば、今週ももしかしたら計画停電が実施されないかもしれない。桜の季節から梅雨くらいまでは、気候が良ければ暖房も冷房も必要ないからだ。
しかし、計画停電がない期間も、たぶんそう長くは続かないだろうと思う。
政府と経済界は、夏の計画停電に備えて時差出勤や、休日を持ち回り制にして、平日に集中する電力の分散を検討するということらしいが、いろいろと案はあっても決定するまでには難航もありえそうだ。
『政府・経済界が今夏の計画停電回避で一致、制限めぐり調整難航も』
asahi.com 2011年4月4日18時15分
http://www.asahi.com/business/news/reuters/RTR201104040073.html
また、エネルギー関連の化学工学会の試算では、工場や学校などの操業時間を工夫したり、電力ピーク時に休み時間を長くとる、在宅勤務を多くするなどの工夫をすることで、夏場の計画停電を回避できると発表したらしい。
『「夏の計画停電は避けられる」 化学工学会の提言が大反響 』
JCASTニュース 2011/4/ 4 21:06
http://www.j-cast.com/2011/04/04092164.html
福島の原発に代わる電力供給は、一時的に火力発電に頼るということにはなっているようだが、首都圏にある火力発電が恒久的に活動できるという見方は、CO2削減などの見地から長期化は難しいのではないかと思う。
それでも、火力発電所が動かなければ、福島の原発に代わる電力の確保は難しい状況だ。
東京に本社が集中しているという理由で、現在東京に計画停電が行われないということであれば、夏に向けて経済界やエネルギー関連団体などの協力は必須だと思う。
化学工学会の記事にもあるが、インターネットが整備されている状態であれば、この機会に在宅勤務がもっと普及してもいいのではないかと思った。
地震のあった直後も思ったが、交通機関が復旧するまで、在宅勤務で仕事をしている人が知り合いにも何人かいた。
それで仕事を回せるのであれば、出勤日数自体を減らすのも一つの方法だと思う。
在宅勤務や、時間交代制勤務については、ヨーロッパではすでに実践されている国もあるし、日本でもエネルギー削減に向けて検討の声も20年も前からあがっていた。
にも関わらず、「いろいろと難しい」などと言い訳ばかりで、ちっとも実施に移行する気配がなかった。
原発の地震や津波に対する見解だって、言い訳ばかりでちっとも対策を練らなかった結果がこれだ。
太陽力にしても風力にしても、実際にはうまく稼動できていない例も多く、日本のエネルギー対策はこれまで「使う」のを補う方向ばかりで、節電には目を向けてこなかったのではないか。
原発事故のお粗末さを見本に、日本のエネルギー対策を国をあげて取り組む必要があるのだと思う。
福島原発の復旧が見込めないのであれば、首都圏は今後数年単位で、大幅な電力供給の削減になるだろう。
原子力に頼らない電力供給というのも必要だろうが、実践的節電というのも、私がスーパーマーケットの暗さになれるのと同じように、現実的に必要に迫られているのではないか。
3月24日の停電以降、ずっと計画停電は実施されず。
暖房需要が減ったことと、火力発電所が動き始めたからとの理由だった。
停電がしばらくなくなったことで、停電が自分の気持ちにかなりの負担になっていたことを知る。
停電になれば、お店も美容院も病院も営業しない。その時間だけというところもあるし、停電が日中に行われる日は営業そのものがなくなるところもある。
停電も朝方や昼ならいいのだが、旦那の帰宅時間に停電時間が重なると、帰路の半分くらいは信号がストップしているので、事故が心配で落ち着いていられない。
一人、真っ暗な中で心配しながら帰りを待つのは、精神的にも良くない。
そういう夜から開放されるということだけでも、計画停電がない期間が続くのは嬉しい。
先週に、自分の状態があまりにも不安定なので、パソコンをつけるのを辞めた。情報が多すぎて、自分で処理しきれなくなったからだ。
友達から携帯に心配のメールをいただいたりもしたが、その返事を入力するのに数時間かかる。状況を伝えようとするとものすごい長文になり、かといって「大丈夫、心配しないで」と配慮できる状態でもなかったらしい。
後で自分の返信を見て、あまりのひどさにさらに落ち込んだりもした。
一週間近くパソコンをつけなかったことで不便も感じたが、特に支障はなかった。地震以来仕事は入れていないし、パソコンをつける必要性もない。
停電もなかったし、必要な情報も必要でない情報も入らないことは、不安よりも開放感の方が大きかったかもしれない。
それでも、テレビのニュースは見ていたので、情報を完全に遮断していたわけではない。
どんどんと露呈される東電の事故対応の鈍さと、日本には本当の意味で原子力設備の専門家などいないのだろうか、という気持ちがいつもテレビの前にあった。
毎日テレビに出てくる原子力の専門家や、私たちがつくばで出会った原子力関連の研究者など、こんなときに何故知恵を出すような動きがないのかが不思議だ。
水を止めるのに、吸水性ポリマーと一緒におがくずと新聞紙というお粗末な顛末を見て、「順番が違うだろう」と家の中で怒号が響く毎日だ。
しかし、避難所の様子や被災者のドキュメントなどは、平静に見ていることができない。旦那も「最近、ああいうのを見ると涙が出てくる」という。
自分は被災していないつもりでも、実際に地震のゆれを感じ、地震の影響を生活に受けている私たちの気持ちは、阪神淡路や中越、奥尻島の地震のときとは明らかに違う。
被災の現実感と中途半端な距離が、心のバランスにつながっているような感覚。
こういう気持ちでいるのは、私たちだけではないような気がする。
阪神淡路のとき、私はパソコン通信(インターネットの前身のネット環境)のチャットをよく利用していて、そこでよく会う人の中には関西の人も多かった。
当時、関西の人たちは関東で地震などがあると、口をそろえて「関西は地震が少ないから、よくわからない」と言い、中には顰蹙を買う人もいた。
しかし、阪神淡路大震災の起きた後、当然のことながら状況は一変した。
つい先日まで「地震の怖さをわからない」と言っていた人も、地震がいかに怖いか、あんな大きな地震は体験してみないとわからない、というようなことを言ったりしていた。
中には、地震のオーソリティみたいになっている人もいて、関東の地震の多い地域の人から失笑を買ったりもしていた。
それでも、どうしても、あの恐怖を伝えないではいられない、という感じだった。
時間が経って、被害の大きかった地域の人がネットに戻ってきたとき、地震のことを聞いても「大変だった」「怖かった」とは言うが、あまり多くを語ろうとする人は少なく、被害の大きかった地域の人たちよりも、その周辺の人たちの方が地震の恐怖について語ることが多かった。
こういうのは、被災が大きかった人は、語る言葉をなくしてしまい、その周辺で現状をある意味客観的に肌で感じた人は、語らずにはいられないのかもしれない。
あの時はそのギャップに驚いたりもしたが、自分もその渦中にいて「あれはこういうことだったのかもしれない」と思ったりする。
この日曜日は、一週間ぶりに買い物に行った。
妹が先々週に野菜を送ってくれたので、買い物に行く必要がなかったからだ。
久しぶりに買い物に行っても、暗い店内を見回して必要なものを購入するが、なんとなく買い物をしたい気分になれない。
店内が暗いと、人が多くても活気が感じられないのだ。
ふだん家にいても、使わない部屋や廊下の電気を切ったり、居間の電灯を半分にしたりして、ふだんよりも暗い場所で生活している。
それでも、スーパーマーケットに行くと、いかに自分がそれまで明るい場所に慣れ切っていたのかが、身にしみて自覚させられてしまう。
節電自体は良いことだと思うので、停電があってもなくてもこれくらいの明るさでいいと思う反面、心のどこかで暗い気持ちになってしまう。
自分自身、早くこの暗さになれたいと思う。
ふだんは買い物しない百貨店の食品売り場で、茨城県産のロメインレタスとリーフレタスが、2把で100円で売られていた。
地震前、ロメインレタスなどはそこの売り場で、1把で300円近い値段で売られていた。
風評被害のために仕入れ値自体が安くなっているのだと思うが、この値段には素直に喜べなかった。
この値段では、たぶん農家にはいくらも収入にはならないだろうからだ。
それでも、茨城県産の野菜が百貨店で取り扱いがあるということは、とてもうれしかった。
売り場の一番目立つ場所に山積みされていたが、半分ほどなくなっていて、購入する人もいることが実証されていた。
この状態であれば、今週ももしかしたら計画停電が実施されないかもしれない。桜の季節から梅雨くらいまでは、気候が良ければ暖房も冷房も必要ないからだ。
しかし、計画停電がない期間も、たぶんそう長くは続かないだろうと思う。
政府と経済界は、夏の計画停電に備えて時差出勤や、休日を持ち回り制にして、平日に集中する電力の分散を検討するということらしいが、いろいろと案はあっても決定するまでには難航もありえそうだ。
『政府・経済界が今夏の計画停電回避で一致、制限めぐり調整難航も』
asahi.com 2011年4月4日18時15分
http://www.asahi.com/business/news/reuters/RTR201104040073.html
また、エネルギー関連の化学工学会の試算では、工場や学校などの操業時間を工夫したり、電力ピーク時に休み時間を長くとる、在宅勤務を多くするなどの工夫をすることで、夏場の計画停電を回避できると発表したらしい。
『「夏の計画停電は避けられる」 化学工学会の提言が大反響 』
JCASTニュース 2011/4/ 4 21:06
http://www.j-cast.com/2011/04/04092164.html
福島の原発に代わる電力供給は、一時的に火力発電に頼るということにはなっているようだが、首都圏にある火力発電が恒久的に活動できるという見方は、CO2削減などの見地から長期化は難しいのではないかと思う。
それでも、火力発電所が動かなければ、福島の原発に代わる電力の確保は難しい状況だ。
東京に本社が集中しているという理由で、現在東京に計画停電が行われないということであれば、夏に向けて経済界やエネルギー関連団体などの協力は必須だと思う。
化学工学会の記事にもあるが、インターネットが整備されている状態であれば、この機会に在宅勤務がもっと普及してもいいのではないかと思った。
地震のあった直後も思ったが、交通機関が復旧するまで、在宅勤務で仕事をしている人が知り合いにも何人かいた。
それで仕事を回せるのであれば、出勤日数自体を減らすのも一つの方法だと思う。
在宅勤務や、時間交代制勤務については、ヨーロッパではすでに実践されている国もあるし、日本でもエネルギー削減に向けて検討の声も20年も前からあがっていた。
にも関わらず、「いろいろと難しい」などと言い訳ばかりで、ちっとも実施に移行する気配がなかった。
原発の地震や津波に対する見解だって、言い訳ばかりでちっとも対策を練らなかった結果がこれだ。
太陽力にしても風力にしても、実際にはうまく稼動できていない例も多く、日本のエネルギー対策はこれまで「使う」のを補う方向ばかりで、節電には目を向けてこなかったのではないか。
原発事故のお粗末さを見本に、日本のエネルギー対策を国をあげて取り組む必要があるのだと思う。
福島原発の復旧が見込めないのであれば、首都圏は今後数年単位で、大幅な電力供給の削減になるだろう。
原子力に頼らない電力供給というのも必要だろうが、実践的節電というのも、私がスーパーマーケットの暗さになれるのと同じように、現実的に必要に迫られているのではないか。
◇計画停電二十五日目。計画停電打切り宣言と、「消えた原子力災害用ロボット開発」の記事。 ― 2011年04月11日 00時57分38秒
2011年4月8日金曜日 計画停電二十五日目。
前日の4月7日は、自治体の防災有線が、計画停電について二度情報を流した。
お昼頃の放送では、明日も計画停電を行わないということ。そして、夕方暗くなってから、計画停電を10日まで行わないことを放送した。
その深夜、やっと電気や水道が通り始めた東北を、再びM7.4という地震が襲った。
それまでの余震だと、神奈川あたりでは体感しているんだか判らないくらいだったのが、この日の地震ははっきり横にゆれて、窓ガラスがゴトゴトと音を立てていた。
そして次の日の、4月8日に東京電力と政府は、実質6月3日まで計画停電を行わないことを発表した。
『計画停電の原則不実施と今夏に向けた需給対策について』
平成23年4月8日 東京電力株式会社プレスリリース
http://www.tepco.co.jp/cc/press/11040802-j.html
『東電、6月3日まで原則打ち切り 』
2011.4.8 12:09 MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110408/trd11040812100005-n1.htm
3月14日から開始された計画停電で、私の住む第1グループで実際に停電になったのは10日ほどのことだ。
今振り返ってみると、停電や節電自体はたいしたことはないのだが、あの大きな地震の後の不安の中の停電というのは、不安ともなんとも説明のつかない感情に支配されていたような気がする。
その感情が今はなくなったかというとそうでもなく、感情の起伏が激しかったり、被災地の情報を直視できない状況は今も続いている。
そういう精神状態の中での停電は、苦痛だった。
みんなが「自分のできること」を探している中で、「自分のできること」を強制されているような気がしたりもした。
ACの「今、わたしができること」というCMも、なんだか「できること」ではなく、「しなければならない」「しないのはおかしい」みたいな風潮に代わってきて、自分が本当にできることってなんだろうと考えることすら嫌になっていった。
いまだに避難を強いられている人たちがいて、停電はあっても普通に生活できている自分が、こんな風に思うこと自体がだめなことなのではないかと思ったりもした。
でも、停電がしばらくは行われず、夏場のピーク時の電力確保については、様々な人が様々な見方はしているけれども、とりあえずは、暗い部屋で不安な気持ちで過ごす日々からは開放されるようだ。
地震自体はまだ予断は許さず、今回の地震で別な地域での地震の懸念なども、新聞などで目にするようにもなってきたが、とりあえずは自己の情報統制を続けることで、少し落ち着いた気持ちで過ごすことができるのではないかと思う。
もし梅雨時期に、やはり計画停電を行うということになっても、次回は今のような気持ちではなく、停電自体を楽しめるくらいの気持ちになっていたいと思う。
地震や計画停電が、自分にこんなに大きな影響を与えるなんて思ってもみなかったので、最初は停電という未曾有の経験を記しておけたらという気軽な気持ちから書き始めたのだが、それがそれだけにとどまらなくなってしまったことに、自分自身戸惑いを感じた。
しばらくは、停電という自分の生活に直結した問題とは離れて、考えることができればと思う。
これを書いている4月10日日曜日、統一地方選挙の投票日だった。
投票会場で選挙公報を眺めながら、最後まで誰に入れるか逡巡した。
誰も投票したと思う人が、いなかったからだ。
投票所の横のポスター掲示板の前には、ぶつぶつと独り言を言う若い男性がいて、10分以上迷っている様子だった。
私たちもさんざん迷って投票した。
私が投票した人は、知事も県議も落選したようだったが、かえってこんな気持ちで投票した人に当選してほしくないとさえ思っていたので、内心複雑な気持ちだった。
帰宅して日本経済新聞のWeb版を読んでいて、こんな記事を見つけた。
『原発「安全神話」に葬られた日本製災害ロボット』
編集委員 滝順一
2011/4/10 16:17 日本経済新聞 電子版
http://www.nikkei.com/biz/focus/article/g=96958A9C93819499E2EBE2E2978DE2EBE2E6E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;p=9694E3E6E2E7E0E2E3E2E0E7E3E5
この記事は、日本経済新聞の電子版の会員でなければ読むことができないので、全文紹介ができないが、概要はこういうことだ。
日本のロボット技術は最高峰と言われているのに、いざ原子力災害があったときに、なぜ日本のロボット技術が活躍の場を得られないのか。
それは、11年前の東海村の臨界事故の後に、国が30億円の予算をかけて原子力対応のロボット開発プロジェクトに着手したのにも関わらず、「原子力災害ロボットが必要になる事態は日本では起きないから、必要ない」という電気業界の一言で開発が打ち切られ、その時開発されたロボットは現在、東工大の玄関モニュメントと化している。
という話である。
コンピュータの回路は放射能に弱く、原子力対応の事故に通常の災害用ロボットが使用できないのは、そのためらしい。
原発からもれる水をせき止めるのに、おがくずや新聞紙まで用いたという話を聞いて、誰もが「ハイテク日本の技術がなぜこのような場で活かされないのか」と疑問に思っただろうということも書かれている。
我が家でも、日本の先進技術を紹介する番組などで、再三日本の災害対応ロボットの話題が取り上げられたり、毎年ロボット甲子園として未来の技術者を育てる取り組みがされているにも関わらず、なぜそういった話題がいっさい聞こえてこないのか不思議だった。
そしてこの記事を見て、愕然としてしまった。
「原子力災害ロボットが必要になる事態は日本では起きないから、必要ない」
という決め付けは、原子力施設で働く人に共通して存在する意識だ。
原子力に限らず、きわめて日本人的意識であるともいえるかもしれない。
日本は地震が多く、首都圏を襲う巨大地震や富士山噴火などの話が絶えないのに、「絶対安全」という感覚がどこから生まれてきていたのか。
「いつかは今ではない」、「そのうち誰かがやるだろう」、「よく話には聞くけど、自分の身にふりかかるような気がしない」というのは、日本人の三大寝言だ。
安全神話と言われた日本の原子力設備の神話がやぶられ、それが虚構であったことがさらけ出された今、「絶対安全」など存在しないということを身をもって知ることになった。
東海村のJOCの臨界事故だって、原子力事故としては小さいものではない。
科学プロジェクトに30億という予算が組まれるということも、本来なら内容の重要性を物語っている。
しかし、研究というのは、それ自体を実用化させるため、検証にこぎつけるまでには、大変なお金と時間がかかる。
東海村の事故が、東京電力の原子力発電所でおきたものであれば、たぶん話は別だっただろうと思う。
だがあれは、東京電力とは違う核燃料施設でおきた事故だった。
福島の原子力発電所から近い場所で起きた事故として、東京電力としては思い出したくないことだったかもしれない。
だからそこよけい、国がやっと原子力施設の危機管理の第一歩として、東海村の事故を活かして次に進もうとしたものを、電力会社の寝言で全て終わらせてしまったことや、プロジェクトをたちあげたはずの国が、そのことをたいして重要に考えない事実は、民主党の仕分けで「来るかどうかわからない地震にお金をかけられない」と言った発言に直結していると思った。
プロジェクトを立ち上げておしゃかにしたのは自民党だが、結局は政治家や官僚の目は、原発に限らず、全ての危機管理にその程度の意識しか持ち合わせていないということだ。
今回の原発の事故で、それがそのまま「安全」の基準になっていた現実に、はっきりと目を向けなければならなくなった。
しかも、福島原発の答えは、急を要している。
対応が後手後手に回り、フットワークの悪さと責任回避ばかりが表立って見える今の政府が、総理得意の理系の計算能力を発揮してくれるのはいつのことなのか。
管総理には是非、出身大学の玄関に飾られているロボットを見て、もう一度襟を正してほしいと思う。
民主党が崩壊してしまうその前に。
前日の4月7日は、自治体の防災有線が、計画停電について二度情報を流した。
お昼頃の放送では、明日も計画停電を行わないということ。そして、夕方暗くなってから、計画停電を10日まで行わないことを放送した。
その深夜、やっと電気や水道が通り始めた東北を、再びM7.4という地震が襲った。
それまでの余震だと、神奈川あたりでは体感しているんだか判らないくらいだったのが、この日の地震ははっきり横にゆれて、窓ガラスがゴトゴトと音を立てていた。
そして次の日の、4月8日に東京電力と政府は、実質6月3日まで計画停電を行わないことを発表した。
『計画停電の原則不実施と今夏に向けた需給対策について』
平成23年4月8日 東京電力株式会社プレスリリース
http://www.tepco.co.jp/cc/press/11040802-j.html
『東電、6月3日まで原則打ち切り 』
2011.4.8 12:09 MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110408/trd11040812100005-n1.htm
3月14日から開始された計画停電で、私の住む第1グループで実際に停電になったのは10日ほどのことだ。
今振り返ってみると、停電や節電自体はたいしたことはないのだが、あの大きな地震の後の不安の中の停電というのは、不安ともなんとも説明のつかない感情に支配されていたような気がする。
その感情が今はなくなったかというとそうでもなく、感情の起伏が激しかったり、被災地の情報を直視できない状況は今も続いている。
そういう精神状態の中での停電は、苦痛だった。
みんなが「自分のできること」を探している中で、「自分のできること」を強制されているような気がしたりもした。
ACの「今、わたしができること」というCMも、なんだか「できること」ではなく、「しなければならない」「しないのはおかしい」みたいな風潮に代わってきて、自分が本当にできることってなんだろうと考えることすら嫌になっていった。
いまだに避難を強いられている人たちがいて、停電はあっても普通に生活できている自分が、こんな風に思うこと自体がだめなことなのではないかと思ったりもした。
でも、停電がしばらくは行われず、夏場のピーク時の電力確保については、様々な人が様々な見方はしているけれども、とりあえずは、暗い部屋で不安な気持ちで過ごす日々からは開放されるようだ。
地震自体はまだ予断は許さず、今回の地震で別な地域での地震の懸念なども、新聞などで目にするようにもなってきたが、とりあえずは自己の情報統制を続けることで、少し落ち着いた気持ちで過ごすことができるのではないかと思う。
もし梅雨時期に、やはり計画停電を行うということになっても、次回は今のような気持ちではなく、停電自体を楽しめるくらいの気持ちになっていたいと思う。
地震や計画停電が、自分にこんなに大きな影響を与えるなんて思ってもみなかったので、最初は停電という未曾有の経験を記しておけたらという気軽な気持ちから書き始めたのだが、それがそれだけにとどまらなくなってしまったことに、自分自身戸惑いを感じた。
しばらくは、停電という自分の生活に直結した問題とは離れて、考えることができればと思う。
これを書いている4月10日日曜日、統一地方選挙の投票日だった。
投票会場で選挙公報を眺めながら、最後まで誰に入れるか逡巡した。
誰も投票したと思う人が、いなかったからだ。
投票所の横のポスター掲示板の前には、ぶつぶつと独り言を言う若い男性がいて、10分以上迷っている様子だった。
私たちもさんざん迷って投票した。
私が投票した人は、知事も県議も落選したようだったが、かえってこんな気持ちで投票した人に当選してほしくないとさえ思っていたので、内心複雑な気持ちだった。
帰宅して日本経済新聞のWeb版を読んでいて、こんな記事を見つけた。
『原発「安全神話」に葬られた日本製災害ロボット』
編集委員 滝順一
2011/4/10 16:17 日本経済新聞 電子版
http://www.nikkei.com/biz/focus/article/g=96958A9C93819499E2EBE2E2978DE2EBE2E6E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;p=9694E3E6E2E7E0E2E3E2E0E7E3E5
この記事は、日本経済新聞の電子版の会員でなければ読むことができないので、全文紹介ができないが、概要はこういうことだ。
日本のロボット技術は最高峰と言われているのに、いざ原子力災害があったときに、なぜ日本のロボット技術が活躍の場を得られないのか。
それは、11年前の東海村の臨界事故の後に、国が30億円の予算をかけて原子力対応のロボット開発プロジェクトに着手したのにも関わらず、「原子力災害ロボットが必要になる事態は日本では起きないから、必要ない」という電気業界の一言で開発が打ち切られ、その時開発されたロボットは現在、東工大の玄関モニュメントと化している。
という話である。
コンピュータの回路は放射能に弱く、原子力対応の事故に通常の災害用ロボットが使用できないのは、そのためらしい。
原発からもれる水をせき止めるのに、おがくずや新聞紙まで用いたという話を聞いて、誰もが「ハイテク日本の技術がなぜこのような場で活かされないのか」と疑問に思っただろうということも書かれている。
我が家でも、日本の先進技術を紹介する番組などで、再三日本の災害対応ロボットの話題が取り上げられたり、毎年ロボット甲子園として未来の技術者を育てる取り組みがされているにも関わらず、なぜそういった話題がいっさい聞こえてこないのか不思議だった。
そしてこの記事を見て、愕然としてしまった。
「原子力災害ロボットが必要になる事態は日本では起きないから、必要ない」
という決め付けは、原子力施設で働く人に共通して存在する意識だ。
原子力に限らず、きわめて日本人的意識であるともいえるかもしれない。
日本は地震が多く、首都圏を襲う巨大地震や富士山噴火などの話が絶えないのに、「絶対安全」という感覚がどこから生まれてきていたのか。
「いつかは今ではない」、「そのうち誰かがやるだろう」、「よく話には聞くけど、自分の身にふりかかるような気がしない」というのは、日本人の三大寝言だ。
安全神話と言われた日本の原子力設備の神話がやぶられ、それが虚構であったことがさらけ出された今、「絶対安全」など存在しないということを身をもって知ることになった。
東海村のJOCの臨界事故だって、原子力事故としては小さいものではない。
科学プロジェクトに30億という予算が組まれるということも、本来なら内容の重要性を物語っている。
しかし、研究というのは、それ自体を実用化させるため、検証にこぎつけるまでには、大変なお金と時間がかかる。
東海村の事故が、東京電力の原子力発電所でおきたものであれば、たぶん話は別だっただろうと思う。
だがあれは、東京電力とは違う核燃料施設でおきた事故だった。
福島の原子力発電所から近い場所で起きた事故として、東京電力としては思い出したくないことだったかもしれない。
だからそこよけい、国がやっと原子力施設の危機管理の第一歩として、東海村の事故を活かして次に進もうとしたものを、電力会社の寝言で全て終わらせてしまったことや、プロジェクトをたちあげたはずの国が、そのことをたいして重要に考えない事実は、民主党の仕分けで「来るかどうかわからない地震にお金をかけられない」と言った発言に直結していると思った。
プロジェクトを立ち上げておしゃかにしたのは自民党だが、結局は政治家や官僚の目は、原発に限らず、全ての危機管理にその程度の意識しか持ち合わせていないということだ。
今回の原発の事故で、それがそのまま「安全」の基準になっていた現実に、はっきりと目を向けなければならなくなった。
しかも、福島原発の答えは、急を要している。
対応が後手後手に回り、フットワークの悪さと責任回避ばかりが表立って見える今の政府が、総理得意の理系の計算能力を発揮してくれるのはいつのことなのか。
管総理には是非、出身大学の玄関に飾られているロボットを見て、もう一度襟を正してほしいと思う。
民主党が崩壊してしまうその前に。
◇今年の花見 ― 2011年04月19日 03時43分52秒
横浜大岡川の桜並木
いつもは花粉を敬遠して、桜は夜に観に行くのだが、今年は少し足を延ばして、電車に乗って桜を観にいった。
花粉の飛散が激しくなる前に帰宅するように、早起きをして早朝から観にいった。
横浜の大岡川は、弘明寺あたりから川の沿道の両側に桜が植えられており、見ごろの時期には桜木町から船で川を上ってみたりできるツアーもある、桜の名所だ。
今年は4月10日頃が見ごろで、震災による自粛で夜の灯明とライトアップは中止されたものの、沿道には早くから人が出ていた。
弘明寺で電車を降り、弘明寺商店街の中ほどにある桜並木を、海に向かって歩く。
桜はほぼ満開で、どの枝も川に向かって枝を広げるように剪定されている様子。
途中途中にある橋から眺める景色は、圧巻だ。
途中、護岸のコンクリートの中から生えている桜があったり、護岸のブロックにはいつくばるように寝ている鳩がいて、じっくり観察したりした。
鴨も何羽かいたが、みんな川面か岸で寝ている様子。すでにすっかり朝なのに、ここの鳥たちは春眠暁を覚えずを決め込んでいる。
ある橋のところで、突然大きな鳥が川の中央を飛んでいき、近くの川面に降り立った。
近くで見るとそれは川鵜で、お食事の最中なのか、川に潜っては別な場所から顔を出すので、結局見失って写真に撮ることができなかった。
途中の家の庭では、たくさんの種類の花と出会った。
この日は天気も良くて暖かかったが、チューリップが咲いているのを見て、時期が早いのに驚いたりもした。
せっかくいろいろ撮影したので、名前も知らない花も含めて記録しておく。
いつもは花粉を敬遠して、桜は夜に観に行くのだが、今年は少し足を延ばして、電車に乗って桜を観にいった。
花粉の飛散が激しくなる前に帰宅するように、早起きをして早朝から観にいった。
横浜の大岡川は、弘明寺あたりから川の沿道の両側に桜が植えられており、見ごろの時期には桜木町から船で川を上ってみたりできるツアーもある、桜の名所だ。
今年は4月10日頃が見ごろで、震災による自粛で夜の灯明とライトアップは中止されたものの、沿道には早くから人が出ていた。
| 寝ている鴨 |
弘明寺で電車を降り、弘明寺商店街の中ほどにある桜並木を、海に向かって歩く。
桜はほぼ満開で、どの枝も川に向かって枝を広げるように剪定されている様子。
途中途中にある橋から眺める景色は、圧巻だ。
途中、護岸のコンクリートの中から生えている桜があったり、護岸のブロックにはいつくばるように寝ている鳩がいて、じっくり観察したりした。
鴨も何羽かいたが、みんな川面か岸で寝ている様子。すでにすっかり朝なのに、ここの鳥たちは春眠暁を覚えずを決め込んでいる。
ある橋のところで、突然大きな鳥が川の中央を飛んでいき、近くの川面に降り立った。
近くで見るとそれは川鵜で、お食事の最中なのか、川に潜っては別な場所から顔を出すので、結局見失って写真に撮ることができなかった。
| 護岸で寝ている鳩。落ちないのが不思議。 | 護岸のコンクリートから生えている桜。 |
途中の家の庭では、たくさんの種類の花と出会った。
この日は天気も良くて暖かかったが、チューリップが咲いているのを見て、時期が早いのに驚いたりもした。
せっかくいろいろ撮影したので、名前も知らない花も含めて記録しておく。
| 川面を流れる花びら。 | 岸で寝る鴨。 | |
| パンジー。 | ||
| まだらの木蓮。 | ||
| 古い民家の塀の豆の花。 | 早咲きのチューリップ。 | |
| 花ニラ。 | 花見をする猫。 | |
| こちらも満開のたんぽぽ。 | ムスカリ? | |
| まだらの椿。 | すごく香りのいいクロッカス。 | |
| 青空と木蓮。 |
◇我が家の電気料金統計をとってみた。 ― 2011年04月21日 02時00分01秒

毎年11月分と3月分は比較的電気料金が安い時期だが、今年の3月分と4月分の電気料金が、いつもの年よりもものすごく安くて驚いた。
我が家はパソコンを使用して、家で仕事をすることが多く、一般的な家庭と比較すると、消費電力が普段から多いように思っていたからだ。
特に4月は、今まで見たことがないような数字だったので、これまでの自分の無駄遣いが露呈されて、ショックを受けた。
私たちの地域は、計画停電は3月15日から行われた。
全部で7回あったうち、15日に一回と16日に二回の各3時間づつ、合計9時間の停電があった。
これは3月分の料金に反映されている。
4月分の料金に反映される3月17日~4月19日までの間は、計画停電は4回あった。
4回のうち3回は3時間、1回は1時間半程度だった。合計で10時間半停電していたことになる。
この料金が、過去の電気料金と比較してどうなのかを確認するべく、過去4年間の電気料金を確認し、統計をとってみた。
○我が家の電気料金
我が家の契約は50A。契約種別は重量電灯B。基本料金は1,356円。
統計をとった期間は、2007年1月から2010年12月までの4年間。
50A契約は、入居したときからこのままなので、現在まで契約の変更は行っていない。
月の表記は、料金支払い月は「○月分」とし、その月分の生活期間は前の月の後半~その月の前半とする。
数字は、10の位は四捨五入してある。
2007年1月から2010年12月までの4年間の平均電気料金は、11,500円。
一番電気料金の安かった月は11月分で、平均料金は9,200円。
高かった月は8月分で、15,300円。
高かった月は8月分で、15,300円。
月平均は、3月分が10,600円、4月分は11,200円。
この4年間で3月分で一番料金の高かった年は、2009年の11,600円。
4月分は、2008年の12,000円。
4月分は、2008年の12,000円。
これで見ると、3月分と4月分は、電気料金が高い年でもだいたい平均並みで、今年は非常に料金が安いことがわかる。
去年以前と今年の生活で違うところがあるとすれば、それはエアコンの使用頻度だろう。
去年の夏までは猫がいたので、におい取りのためエアコンをずっと送風状態にしていた。それは通年で行っていたが、猫が8月の終わりに亡くなったので、エアコンをつけっぱなしにする生活もなくなった。
去年の夏は猛暑で、危篤状態が続く猫のために温度管理をしていたせいか、エアコンはフル稼働していた。そのため、梅雨時期の7月分と、猫の危篤がピークだった8月後半時期が反映される9月分の料金は、4年間の中でも過去最高だった。
グラフにしてみると一目瞭然だが、エアコンを使わないことで料金を実感したのは、残暑も済んで冷房すっかりを使わなくなった10月後半の時期が反映される、11月分の料金からだ。
それまでは通年通風状態だったエアコンが使用されず、冬に入っても今年はそれほど寒くなかったので、電気料金はこれまでの平均値よりも11月分と12月分は1,000円、今年の1月分は2,000円ほど安かった。
1月分が劇的に安いのは、我が家はエアコンで暖房を使用することはないため、年末の大掃除のときからエアコンの電源プラグを抜いておいたせいもあるのか。
この傾向は今年に入ってからも続いており、11月からはずっと1,000円~2,000円ほど平均よりも電気料金が安くなっており、寒さが本格化して電気パネル式のストーブを使用していた1月分からの料金でも、平均よりもずっと安くなっている。
これで見ると、我が家はエアコンを通年利用することで、月に1,000円以上の電気料金を支払っていたことになる。
それらを差し引いても、今年の3月分と4月分の電気料金はとても安い。
節電を始めたのは4月分に入ってからのことなので、4月分のいつもの半分の額というのは、計画停電+節電の賜物だろう。
○節電
「暮らしのAllAboutアーカイブス」に、『家電の待機電力ワースト3』という記事がある。
これによると、家庭の中の消費電力は消費電力の7.2%を占め、その割合はAV機器30%、給湯機器29%、IT機器19%、以下照明機器、空調機器などとなる、と書かれている。
この中でも、一番電力を使用するのは、ガス給湯器の待機電力であるらしい。
我が家もガス給湯器なので、計画停電開始後はまめに消すようにしている。
また、計画停電中はHDDレコーダーの録画予約をしていても、途中で停電になるとHDDが壊れる可能性があるため、予約自体を全て取りやめ、その都度停電が行われないときだけ予約するようにした。
HDD関連が壊れると痛いので、計画停電期間中はパソコンを使う頻度も少なくなった。
給水サーバーの保温を辞める、使わない部屋の電気を消す、廊下のクリプトン電球を蛍光灯に換えるなど。蛍光灯も4本使用する部屋は2本に、2本使用する部屋は1本だけに減らした。
廊下のクリプトン電球はLEDに変更したかったが、天井に埋め込み式のためLEDでは熱がこもりすぎるということで、蛍光灯にした。
それと、これは以前からやっているが、お風呂はできるだけ家族と一度に入る。ご飯の保存はおひつを利用している。
料理も、できるだけ一度にすますようにしている。
朝食を作るのと一緒に昼食の準備もして、夕食のときにお弁当の準備もするという感じ。
それと、5月には50Aを40Aに下げようと考えている。
アンペアを下げても実質的な節電にはならないが、使える電力の幅が下がるので、使いすぎないということにはつながる。
この50Aの契約は、全ての部屋にエアコンをつけるのを想定しているが、うちはエアコンは1台しかなく、もう1台は寝室にある冷房器だ。これらを同時に使用することは、ほとんどない。
家族がみんな家でパソコンで仕事をすることがあるので、大きいままにしてきたが、以前は30Aで過ごしていたので、40Aでも問題はないだろう。
30Aにしないのは、以前の古いマンションとは違い、今の部屋は自分で想定していない電気が使用されている可能性があるからだ。
給湯器もよく考えればそうだし、モニター付のインターフォン、共通スペースの電気など、今回ブレーカーを落としてみて気づいたところがけっこうあった。
部屋の電気が、どのブレーカーがどこの電気につながっているかを確認できたのも、ちょっとした収穫だったかもしれない。
○今後の電気料金
『計画停電等に伴う電気料金の割引について』
平成23年4月8日 東京電力プレスリリース
http://www.tepco.co.jp/cc/press/11040803-j.html
これで見るとおり、東京電力は5月分の電気料金から、計画停電が行われた地域に対して、電気料金の割引を行うとしている。
割引料は基本料金の4%。我が家は1,365円の基本料金で、1回分は54.6円。
7回停電があったので、382.2円割引されるらしい。
あれだけ大騒ぎして382円。
しかも、うちは50Aだからまだ多い方だ。一般的には30Aくらいだろうか。
こんな微々たる割引では、まったくお得感がない。
消費税にも満たないこの割引額は、どこから出てきたのだろうか。
計画停電で商売あがったりになった人たちもいる中で、こんな微々たる金額を返してもらっても、割に合わない感しか残らない。
返してくれるだけましだと思うか、こんなだったら返してもらわない方がいいと思うか。
それでも、節電でさらに電気料金を節約でき、過去の電気消費量の統計をとるような気持ちになったのは、怪我の功名といえるだろうか。
今後もできるだけ節電にはげんで、平均10,000円切りを目指したい。
◇ディナゲストの供給についての情報 ― 2011年04月22日 02時17分12秒
3月29日に、子宮内膜症治療薬「ディナゲスト」が、発売元の持田製薬の工場が震災によって壊滅的被害を受け、その影響で供給が危ぶまれているという記事を書いた。
◇治療薬がなくなりそう。 ―
2011年03月29日 04時05分16秒
http://makura.asablo.jp/blog/2011/03/29/5763523
その後、メールをいただいたり、コメントをいただいたりしていたが、多くは私と同じように子宮内膜症の治療を続けていて、薬がなくなることに困惑しているという内容だった。
また、担当医や薬剤師から、薬の供給が困難であることを受けて、検索ワードでここの記事を閲覧される方も多かった。
今回、持田製薬の平成23年4月19日発表のニュースリリースにて、ディナゲストの供給に関して公式に発表されているので、ここにリンクを貼っておくことにした。
持田製薬株式会社
2011年度ニュースリリース一覧
http://www.mochida.co.jp/news/index.html
平成23年4月19日発表ニュースリリース
「東日本大震災の影響に関するお知らせ(第四報)-子宮内膜症治療剤「ディナゲスト」の供給について-」(PDF)
http://www.mochida.co.jp/news/2011/pdf/0419.pdf
PDFを見られない方のために、概要だけをかいつまむと
今回の震災により持田製薬工場株式会社の本社工場(栃木県大田原市)が被災し、供給ができない状態になっている口径剤及び医薬品に関して、包装工程及び生産工程が徐々に回復してきており、一部は外部委託にて供給ができるような措置をとったとこと。
(持田製薬ニュースリリース「東日本大震災の影響に関するお知らせ(第三報)」平成23年4月18日発表」より)
その中で、ディナゲストについては外部委託の措置をとり、早急に供給できる体制を整えているとのこと。
これについては、上記リンクの第四報に別に詳細を発表している。
以下、ニュースリリースの内容を一部抜粋のうえ引用する。
「ディナゲスト錠1mg」につきましては、緊急措置的対応として在庫仕掛品のバラ包装品での出荷対応をとることとし、「バラ包装(56 錠)」の出荷が4月下旬より開始できる見込みとなりましたのでお知らせいたします。また、十分な供給量を確保すべく、本剤生産の一部を外部委託いたしました。5月下旬より委託製造分が供給に寄与してくる見込みです。なお、従来のPTP 包装品の生産はPTP 包装ラインの復旧を待っての再開となりますが、その時期は6月下旬頃の見込みです。(引用ここまで)
※平成23年4月19日発表ニュースリリース
「東日本大震災の影響に関するお知らせ(第四報)-子宮内膜症治療剤「ディナゲスト」の供給について-」
http://www.mochida.co.jp/news/2011/pdf/0419.pdf
より一部抜粋
やはり、代替薬がまだないということと、女性の精神と生活に直結する症状なので、薬がないということは処方されている人にとっては非常に不安だった。
これで、少しめどが見えてきたことに、ほっとするばかりだ。
◇治療薬がなくなりそう。 ―
2011年03月29日 04時05分16秒
http://makura.asablo.jp/blog/2011/03/29/5763523
その後、メールをいただいたり、コメントをいただいたりしていたが、多くは私と同じように子宮内膜症の治療を続けていて、薬がなくなることに困惑しているという内容だった。
また、担当医や薬剤師から、薬の供給が困難であることを受けて、検索ワードでここの記事を閲覧される方も多かった。
今回、持田製薬の平成23年4月19日発表のニュースリリースにて、ディナゲストの供給に関して公式に発表されているので、ここにリンクを貼っておくことにした。
持田製薬株式会社
2011年度ニュースリリース一覧
http://www.mochida.co.jp/news/index.html
平成23年4月19日発表ニュースリリース
「東日本大震災の影響に関するお知らせ(第四報)-子宮内膜症治療剤「ディナゲスト」の供給について-」(PDF)
http://www.mochida.co.jp/news/2011/pdf/0419.pdf
PDFを見られない方のために、概要だけをかいつまむと
今回の震災により持田製薬工場株式会社の本社工場(栃木県大田原市)が被災し、供給ができない状態になっている口径剤及び医薬品に関して、包装工程及び生産工程が徐々に回復してきており、一部は外部委託にて供給ができるような措置をとったとこと。
(持田製薬ニュースリリース「東日本大震災の影響に関するお知らせ(第三報)」平成23年4月18日発表」より)
その中で、ディナゲストについては外部委託の措置をとり、早急に供給できる体制を整えているとのこと。
これについては、上記リンクの第四報に別に詳細を発表している。
以下、ニュースリリースの内容を一部抜粋のうえ引用する。
「ディナゲスト錠1mg」につきましては、緊急措置的対応として在庫仕掛品のバラ包装品での出荷対応をとることとし、「バラ包装(56 錠)」の出荷が4月下旬より開始できる見込みとなりましたのでお知らせいたします。また、十分な供給量を確保すべく、本剤生産の一部を外部委託いたしました。5月下旬より委託製造分が供給に寄与してくる見込みです。なお、従来のPTP 包装品の生産はPTP 包装ラインの復旧を待っての再開となりますが、その時期は6月下旬頃の見込みです。(引用ここまで)
※平成23年4月19日発表ニュースリリース
「東日本大震災の影響に関するお知らせ(第四報)-子宮内膜症治療剤「ディナゲスト」の供給について-」
http://www.mochida.co.jp/news/2011/pdf/0419.pdf
より一部抜粋
やはり、代替薬がまだないということと、女性の精神と生活に直結する症状なので、薬がないということは処方されている人にとっては非常に不安だった。
これで、少しめどが見えてきたことに、ほっとするばかりだ。























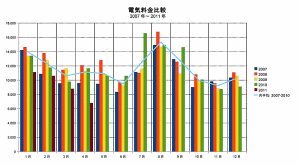
最近のコメント